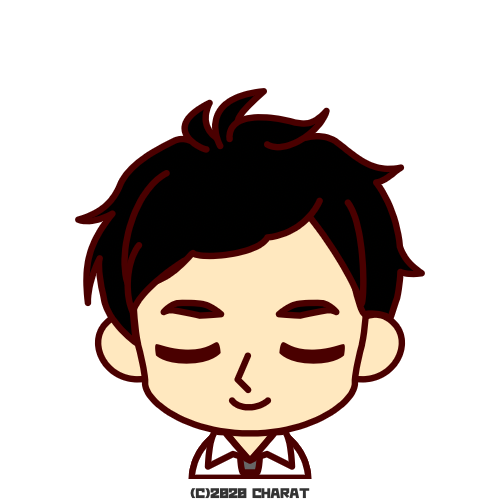全身倦怠感の鑑別は膨大な数になります。
単なるウイルス感染から悪性腫瘍、内分泌疾患、うつ・・・
全てを挙げていけばおそらく100を超えるのではないでしょうか?
それら全てを時間もリソースも限られた救急外来で診断していくことはほぼ不可能です。
では救急外来で全身倦怠感を訴える高齢者を診たときに実際はどうすれば良いか?
「まずは3つの病態を考える」というアプローチを紹介します。
目次
高齢者の全身倦怠感でまず考えるべき3つの病態

膨大な数の鑑別疾患があるのは事実ですが、何かしら“とっかかり”がないと病歴や身体診察、そして検査の方向性が定まりません。
そこで、救急外来で比較的頻度が高い、そして緊急度が高い、という観点から3つの病態をまず考えるというアプローチをおすすめしています。
その3つの病態とは、心不全、貧血、感染症です。
- 心不全
- 貧血
- 感染症
「たった3つで全身倦怠感をカバーできるわけないだろ!」と思われるかもしれませんが、もう少しだけ聞いてください。
あくまでも“とっかかり”となる“病態”なので疾患が3つというわけではありません。
例えば心不全を想定した場合を考えます。
もともと心疾患がある人が体液過剰となってうっ血性心不全をきたす、という病態も想定されますが、救急外来で心不全を考えるならば虚血の除外も考えるはずです。
なので自然と「ECGを取ろう」という発想になります。
高齢者の全身倦怠感の鑑別に心筋梗塞は重要な鑑別ですが、この「心不全を想定する」という考え方をおさえておけば、カバーされます。
貧血も同様で、貧血というワードから鑑別をたどっていけば緊急性の高い急性の消化管出血はもちろん、高齢者であれば悪性腫瘍という鑑別を挙げることは難しくありません。
さらに、貧血を想定している以上は血液検査をオーダーすることになります。
そこで電解質異常や血糖値の異常などが見つかれば内分泌疾患なども鑑別に入れて進めていくのです。
あくまでもこの3つの病態は最初の“とっかかり”です。
このとっかかりからまず情報を集めていって、そこからさらに追加された情報をもとにアセスメントを適宜修正していく、という作業がこの全身倦怠感の鑑別では重要です。
ただやはり救急外来では全身倦怠感の診断がつかない、ということもよくある事です。
ではその場合に入院させるかどうか(disposition決定)についてお話ししていきます。
診断がつかない高齢者の全身倦怠感は入院させるべきか

全身倦怠感の診断がつかない、ということは珍しくありません。
その場合に入院させるかどうか、といういわゆるdisposition決定に悩むはずです。
結論から言ってしまうと、「高齢者の原因不明の全身倦怠感」は原則入院させて良いと僕は考えています。
3つの病態から鑑別を挙げる方法で、ある程度は緊急性の高い病態は除外できているはずですが、特に高齢者では不確実な要素は必ずあります。
例えば熱が無いと言っても感染症は完全には否定できませんし、血液培養の結果が出るには少なくとも2−3日かかります。
「今後の経過」という要素も診断には必要になる場合があります。
なので経過観察入院という選択肢は高齢者の全身倦怠感では妥当なオプションです。
もちろん、バイタルサインが全て安定している、ADLが保たれている、同居の家族の見守りが期待できる、などの要素を考慮して外来フォローするというのはありです。
ですが、何らかの不安要素がある場合には入院をためらう必要はないというのが僕の考えです。
状態が悪化しない事や血液培養の結果などを見てから早期退院の判断をすれば、そこまで失うものはないはずです。
まとめ
救急外来での高齢者の全身倦怠感の鑑別について、3つの病態を考えるアプローチとdispositionの考え方についてお話ししました。
もちろんここで紹介した方法が絶対というわけではありません。
ですが、膨大な鑑別疾患を挙げるだけではなかなか診療を進めることは難しいはずです。
あえて最小限の3つの病態に絞ることで、救急外来でのdisposition決定というゴールに効率よく到達できるはずです。